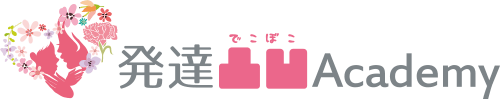「子どもがスプーンを上手に持てない…」
「ご飯を手づかみで食べてしまう」
発達に凸凹のあるお子さんは、手先が上手く使えないこともあり、スプーンやお箸の使い方で悩んでいる親御さんもいらっしゃるでしょう。
良い対応策が見つからないときは、子どもの手の発達段階について、理解を深めてみるといいかもしれません。
ただやみくもに練習させるよりも、新しい視点を取り入れることで、「これが原因なのかもしれない」と思い当たるようになります。
この記事では、「子どものスプーンの持ち方を上達させるにはどうすればよいか?」とお困りの親御さんに向けて、スプーンを上手に持てない原因と対応策をまとめています。
参考になるものがあれば、ぜひお子さんの食事サポートに取り入れてみてください。
- 1. 子どものスプーンの持ち方と手の発達段階について
- 2. 発達障害の子がスプーンを上手に持てない・使えない原因と対応策
- 2.1. 子どもの手の発達に合った持ち方をしていない
- 2.2. 両手が上手に使えない
- 2.3. スプーンが使いにくい
- 2.4. 食材への過敏さが影響している場合も
- 3. スプーンを上手に持てるようになるためにできること4つ
- 3.1. 1.普段から運動や遊びを通して手を使う
- 3.2. 2.両手を使う動作を意識したり、環境を整える
- 3.3. 3.使いやすい食器を使う
- 3.4. 4.正しい持ち方は手を添えながら徐々に教える
- 4. スプーンの練習で無理強いをさせてしまった事例
- 5. お箸を使い始めるタイミング
- 5.1. まずはスプーンがちゃんと使えているか確認
- 5.2. スプーンと併用しながら少しずつ練習する
- 5.3. リングのついた矯正箸は状況に応じて使う
- 5.4. 周りと比べずに進める
- 6. まとめ
子どものスプーンの持ち方と手の発達段階について
どうしてうちの子はスプーンを上手に使えないんだろう?
その原因を探る前に、スプーンやフォーク、箸といった道具の持ち方の発達段階について、確認しておきましょう。
「発達が気になる子への生活動作の教え方(中央法規出版)」によると、子どものスプーンの持ち方は下記1~4の順番に発達していくとされています。
①スプーンをすべての指を使って握るように持つ。(手掌回内握り)

②親指と人差し指を伸ばして持つようになる(手指回内握り)

③親指・人差し指・中指を使って、鉛筆を持つような持ち方に近づく。指先は使わずに手首や肘を動かしている状態(静的三指握り)

④親指・人差し指・中指で正確に持てるようになる。指先を屈伸させて動かせる状態(動的三指握り)

上記を参考に、子どもは今どの段階にいるのか、食事の様子を観察してみてください。これを踏まえて、次の章で原因を探っていきます。
発達障害の子がスプーンを上手に持てない・使えない原因と対応策
発達が気になる子がスプーンを上手に持てない原因としては、以下のようなことが考えられます。
子どもの手の発達に合った持ち方をしていない

前章でお伝えしたように、子どもがスプーンを正しく持てるようになるまでには、4つのステップがあります。
「スプーンの持ち方を正そうとしているけど、上手くいかない」という状況でしたら、お子さんの手の発達に合った持ち方をしていないことが原因かもしれません。
この場合の対応策としてはまず、子どもが自然と手にする持ち方で食事をさせてみましょう。
冒頭でご紹介した本では、
持ち方を先にすすめるのではなく、こぼしが少なくなってきたら次の段階の持ち方を試してみる
発達が気になる子への生活動作の教え方(中央法規出版)
と記されています。
本人が持ちやすい持ち方で食べさせ、食べこぼしの様子を観察します。もし食べこぼしが多いなら、「次の段階に進むには早かった」ということになります。
今子どもに合う持ち方で、存分に食べる経験を積み、こぼさなくなってきたら、次の持ち方を練習してみてください。
両手が上手に使えない

スプーンを持つ手とは反対の手で茶碗や皿に手を添えたりせずに、片手は下に落ちたまま。こんな様子を見せるお子さんもいます。
発達の凸凹が大きいと、両手の協調性が上手く発達していないこともあり、これがスプーンを上手に使えない原因の一つになっていることも考えられます。
この場合の対応としては、「片方の手はお茶碗の横だよ」と伝え続けることも大事ですが、声掛けだけではなかなか伝わりません。大人が手を添えて、手の位置を教えてあげるとよいです。
嫌がる様子を見せたら無理強いする必要はありません。本人が落ち着いて反応してくれるときだけで良いので、気長に伝えていきましょう。
食事以外の場面で、両手を使った活動や遊びを意識することも、両手の協調性を育てるのに有効です。両手を使う遊びについては、後ほど例をご紹介します。
スプーンが使いにくい

食器のサイズや材質が子どもに合っていない。これが原因であることも考えられます。
例えば、
- スプーンの柄が細すぎて、手の中でクルクルと回ってしまう
- プラスチック製だと、おかずが切り分けにくい
ということがあります。
対応策としては、しっかりと握れて、扱いやすく、安定して口元まで持っていけるようなスプーン選びをしてあげることです。
発達障害がある子の場合、力の加減が上手くできない子もいます。
力のコントロールが苦手だと、物を扱うときに力が入りすぎたり、逆に弱すぎたりで、上手に道具を扱えないことがあるため、その子に適した道具選びが大切になってきます。
食材への過敏さが影響している場合も

食材そのものへの過敏さが原因となっていることも考えられます。
発達障害のあるお子さんは、感覚過敏な子も多く、揚げ物の衣がチクチクすると言って嫌がったり、ご飯粒のようなベタベタした触感を嫌がる子もいます。こういったことが原因で、手が上手く使えていないのかもしれません。
この場合、手先の感覚を育ててあげることに加えて、食事そのものにも工夫をすると効果的なこともあります。
子どもの「食べない」お悩みの原因と適切な対応がわかる!
1日3時間で学ぶ「偏食と食事療法」はこちら↓
スプーンを上手に持てるようになるためにできること4つ
この章では、スプーンやフォークといった道具類を上手に使えるように、意識しておきたいことを4つお伝えします。
1.普段から運動や遊びを通して手を使う

手の発達を促すために、日常的に手を動かすことを意識してみてください。
お子さんの好きな遊びがきっかけになれば一番です。子どもが好む遊びは、その時期の発達に必要な遊びだとよく耳にします。できる範囲でよいので、付き合ってあげてください。
手先を使う遊びには、次のようなものがあります。
- 公園の遊具で遊ぶ
- ボール、風船、お手玉投げ
- 新聞紙を破って遊ぶ
- シールを剥がす、貼る
- 手遊び
- 粘土
- ブロック
- 積み木
- お絵かき
- パズル
パズルなどはあえてピースを裏返しにし、表に返す作業だけでも手先をたくさん使うことができます。
楽しく手先を使う機会を作ってあげてください。
訓練だと思わないことが大切です。
親が「やらせる」意識を持ってしまうと、やってくれないことが苦しくなってしまいます。「遊びの先に、成長がある」という気持ちで取り組んでください。
2.両手を使う動作を意識したり、環境を整える
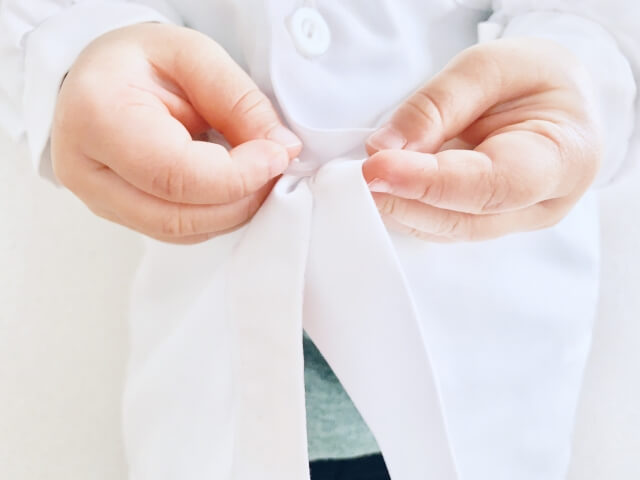
両手が上手に使えていない場合、手の協調性を高めるために、両手を使った活動は役立ちます。
遊びを通してできれば無理がないので、先にご紹介した遊びを取り入れることはもちろん、日々の生活の中でも、子どもが両手を使う動作を増やしてあげるとよいでしょう。
- きんちゃく袋を開く・閉じる
- タオルをたたむ
- ボタンを留める・外す
- 顔を洗う
できそうなことから少しずつ、試してみましょう。食事以外の場面で両手を使う動作が増え、できるようになってくれば、スプーンの使い方にも良い影響が出てくるはずです。
両手が上手く使えるようになるまでは、食器を手で支えることは難しいですから、「できなくてもOK」という気持ちで接してあげてください。それと同時に、食事がしやすい環境を整えておくと、お子さんの負担も減ります。
例えば、すべり止めのあるマットを使うと、食器が動かず食べやすくなります。食器自体にすべり止めが付いているものもありますね。各家庭にあった環境を整えていきましょう。
3.使いやすい食器を使う
使いやすい食器を選ぶことも大事です。スプーン選びのチェックポイントには、次のようなものがあります。
- 握りやすい太さ・素材か
- ご飯やスープをしっかりすくえる深さがあるか
- 子どもの口に入れやすい大きさか
おすすめのスプーンについては、こちらの記事で紹介していますので、参考にしてください。
4.正しい持ち方は手を添えながら徐々に教える

スプーンの持ち方でつまずくケースの多くは、親指・人差し指・中指を使った三指握りに移行する時期かと思います。
どうしても上からスプーンを握ってしまったり、下から握れたとしても掌全体で握ってしまったり。正しい手の向き、指の位置を教えるのは難しいものです。
正しい握り方を教えるときは、手をそっと添えて、無理のない範囲でサポートしてあげてください。
「正しい持ち方は食事中に1回でもできればOK」ぐらいの気持ちで進めましょう。一つのことができるようになるまでの時間は、子どもによって様々です。
兄弟姉妹でも全然違います。根気が必要かもしれませんが、「この子はこういうペースなんだ」という気持ちで、休み休み進めていきましょう。
スプーンの練習で無理強いをさせてしまった事例
ここで、2歳の男の子の事例をご紹介します。この男の子は、クレヨンの持ち方などもぎこちなく、手先を使う動作がとても苦手なお子さんでした。
スプーンもすくう動作が上手くできません。右手にスプーンを持っていても、左手でご飯を掴んで食べてしまうことが多く、お母さんがスプーンにご飯を盛るところまで手伝って食べさせる毎日でした。
ある日保育園の先生から、「給食を手づかみで食べているので、お家でも練習して欲しい」と言われたのをきっかけに、スプーンの練習を始めます。
本人が嫌がる様子を見せても、焦るお母さんはつい、しつこくスプーンの練習を続けてしまいます。その結果、数日後から男の子は夜泣きをするようになり、ここでやっと、子どもに無理強いしていたことに気付きます。

その後はゆっくりペースに切り替え、夕食の最初の一口だけ手を添えてスプーンを使い、その後は本人の好きなように食べてもらうことにしました。
最初の一口だけの練習ですが、「いただきます」をしたら一口スプーンで食べるということを繰り返すうちに、徐々にスプーンで食べる時間が増え、上手に使えるようになりました。
親の都合を押し付けてしまった失敗事例ですが、子どものペースに合わせることの大切さを感じていただけるでしょうか。こういった練習はとても根気のいることですが、親自身のハードルも下げて、子どもを尊重して進めることはとても大切です。
お箸を使い始めるタイミング

スプーンが上手に使えるようになったら、次はお箸ですね。最後に、お箸へ移行する際のポイントいついてお伝えします。
まずはスプーンがちゃんと使えているか確認
箸の練習は、スプーンがある程度使えるようになってから開始します。
目安は、鉛筆を持つような持ち方をするようになったタイミングです。冒頭でご紹介した「静的三指握り」の段階に当たります。この段階に到達したら、食卓にお箸を並べてみましょう。
スプーンと併用しながら少しずつ練習する
「静的三指握り」の段階では、まだ指先だけでお箸を動かすことはできません。お箸だけで食事をするのは難しいため、スプーンも併用して少しずつ練習するのがコツです。
子どものやる気に合わせて、気が乘らないようならスプーンだけ使うなど、臨機応変に対応していきましょう。
リングのついた矯正箸は状況に応じて使う

親指・人差し指・中指にリングの補助がある矯正箸は、とても簡単にご飯が掴め、子どもは喜んで使います。ですがこのタイプの矯正箸は、動かすときの力の使い方が、普通のお箸とは違います。
そのため、普通の箸を持ったときにスムーズに使えず、「上手くいかない」「結局は普通のお箸の使い方を一から練習することになる」といった話もよく耳にします。
「食べることが楽しい」を味わせることが目的なら、リング付きの矯正箸も良いでしょう。
しかし「お箸を正しく使えるようにしたい」といったことが目的であれば、リング補助のないサポート箸か、普通の箸を使う方が、進みは早いかもしれません。
周りと比べずに進める

スプーンと同じで、お箸の練習も子どものペースで進めましょう。
箸を持ち始める時期は、環境に左右されることも大きく、お兄さんお姉さんがいる子は早く持ち始めることもあります。保育園では2歳児クラスからお箸を使い始める園もあれば、幼稚園では年中・年長になってから徐々に移行したりと、様々です。
幼児期のわずか1年前後の違いなのですが、親からすれば「遅れているんじゃないか」と感じてしまうこともあるかと思います。
でもみんなそれぞれ、ペースが違うのが当たり前ですから、心配しすぎずに、お子さんの力を信じてつきあってあげてください。
まとめ
- スプーンの持ち方の段階を知り、子どもに合った持ち方で十分経験を積んでから、次のステップに進む
- 「スプーンや箸が上手に持てない」と感じたら、持てない原因を探ってみる
- 子どもが好きな運動や遊びを通して、体や手を動かすことも大事
- 食器などの食事環境も一度見直してみる
- お箸はスプーンが十分に使えるようになってからでOK
スプーンやお箸を使えるようになるまでに時間がかかると、「大丈夫かな…」と心配になることもあります。
でもどの子も必ず、その子のペースで成長していきます。親の私たちが気長に構え、我が子をサポートしていきたいですね。