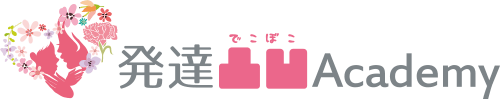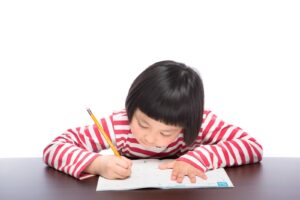「お箸が上手に使えない」
「すぐこぼしてしまう」
子どもの食事に関する悩みは、様々ですね。
上手にお箸やスプーンが使えない原因の一つとして、子どもに適した食器を選べていないということが挙げられます。子どもの手のサイズに合った、使いやすい道具を持たせてあげることは、私たち親ができることの一つです。
この記事では、食事動作の悩みが解決に向かうよう、手先の不器用なお子さんでも使いやすい、おすすめの食器をご紹介しています。
お子さんに合った食器を使って、毎日の食事を楽しくサポートできるよう、参考にしてください。
- 1. 発達障害の子も使いやすいお箸選びのポイント
- 1.1. 子どもの手のサイズに応じたお箸を選ぶ
- 1.2. お箸の素材について
- 1.3. 補助機能付きからスタートして慣れたら補助なしへ移行
- 2. 手先が不器用な子にもおすすめの箸7選
- 2.1. ①エジソンのお箸Ⅰ
- 2.2. ②ののじ はじめてのちゃんとお箸
- 2.3. ③イシダ ちゃんと箸
- 2.4. ④イシダ 子供用矯正箸 三点支持箸
- 2.5. ⑤リッチェル トライ トレーニング箸
- 2.6. ⑥箸匠せいわ 六角知能箸
- 2.7. ⑦子ども用割り箸
- 3. 子どもにお箸の持ち方をどう教えるか
- 4. お箸と併用しよう!スプーン・フォーク選びのポイント
- 4.1. 子どもが持ちやすく食べやすい形状を選ぶ
- 4.2. スプーン・フォークの素材について
- 5. 子ども用おすすめスプーン・フォーク2選
- 5.1. ①エジソンのフォーク・スプーン
- 5.2. ②オクソートット(OXO tot)フォーク&スプーンセット
- 6. 手先の不器用さに関係している感覚統合について
- 6.1. 感覚統合とは
- 6.2. 感覚統合が上手く働くようにできること
- 6.3. お箸の練習が上手くいかないときは、お休みしながらでよい
- 7. まとめ
発達障害の子も使いやすいお箸選びのポイント

子どもがお箸を使い始める時期には個人差があり、2歳頃からスタートする子もいれば、5、6歳頃からという子もいます。
ですので、年齢にこだわる必要はありません。スプーンやフォークを上手に使えるようになり、子ども自身がお箸に興味を示すときが良いタイミングと考えましょう。
では、さっそくお箸を選ぶときのポイントをご紹介します。
子どもの手のサイズに応じたお箸を選ぶ
子ども用お箸は、13~18㎝ぐらいまでの長さがあります。1㎝きざみで販売されているものもあるため、子どもの手に合ったものが見つかりやすいです。
サイズの目安は、利き手の親指と人差し指をL字型にし、それぞれの指先を直線でつないだ長さの1.5倍くらいと考えておくとよいです。

お箸の素材について
お箸の素材には、樹脂製や木製があります。
樹脂製の箸は、熱湯にも強いので長い期間使うことができます。また、木製より軽くて持ちやすいのも特徴です。滑りにくさという点では、木製の方が使いやすいでしょう。
どちらを選ぶかは好みになりますが、どちらの素材でも、食べ物を挟む先端部分に滑り止め加工があるものだと、食材がつかみやすくて良いです。
補助機能付きからスタートして慣れたら補助なしへ移行

最初から普通のお箸を使いこなすお子さんもいますが、補助機能付きタイプからのスタートは、お箸を取り入れやすくて良いでしょう。「お箸で食べる」という成功体験を積んで、慣れてきたら補助機能がないお箸に移行します。
補助機能が付いていても、最初は上手に使いこなせません。子どもがお箸を持つことを嫌がったら、スプーンやフォークに切り替えてあげ、苦手意識を植え付けないようにしてあげてください。
補助機能付きの箸には、親指・人差し指・中指にリングの補助がある箸があります。

このタイプは簡単にご飯が掴め、「楽しく食べる」という経験を積むには便利です。
その一方で、箸を動かすときに力を入れる場所が普通の箸とは違うため、リングなしタイプに移行したときに、スムーズに使えないという声もよく聞きます。このタイプを使う際は、箸の切り替えに時間がかかるかもしれない、ということを考慮しておきましょう。
手先が不器用な子にもおすすめの箸7選

補助機能付きの箸も含め、手先が不器用な子でも使いやすい箸を7つご紹介します。
①エジソンのお箸Ⅰ
リング補助機能があるタイプとして定番の、エジソン箸。2本のお箸が連結しており、食べ物をはさむところには滑り止め加工がされています。
リング付きのタイプは「お箸を使って楽しく食べる」体験を積むには、使ってみてもよいでしょう。
②ののじ はじめてのちゃんとお箸
手を添える位置と指を添える位置の2箇所に、カプラという補助器具がついていて、お箸の開閉をサポートしてくれます。
先端が自然に開くバネ設計になっているため、お箸をにぎることで食べ物を挟むことができます。
普通の箸とほとんど同じ動きをしますので、子どもが自分で正しい持ち方になおしやすい点もメリットです。
③イシダ ちゃんと箸
お箸を使えるようになってきたけれど、正しい持ち方に矯正したいと感じたときに使えるお箸です。シリコンの部分がお箸の持ち方をサポートしてくれます。
中指と人さし指をシリコン部分に沿わせ、両方の指先でお箸を挟み、親指の先をシリコン部分の上にあてることで正しい持ち方を練習することができます。お箸の素材は天然木でうるし塗装、サポート器具のシリコン部分は取り外し可能です。
こちらは右利き用と左利き用が用意されています。
④イシダ 子供用矯正箸 三点支持箸
「ちゃんと箸」と同じメーカーのお箸です。
このお箸には、指を当てる位置すべてにくぼみと目印が付いているのが特徴です。その通りに指を添えることで、自然と正しくお箸を持つことができます。
目印は花や星など、すべて違うマークのため間違えにくく、視覚補助が有効な発達凸凹のある子どもには役立ちそうです。14㎝、15㎝、16.5㎝の3種類があります。
⑤リッチェル トライ トレーニング箸
こちらは、木製のお箸とシリコン製の箸ホルダーがセットになったもの。
この箸にも指を置く場所にくぼみがあり、くぼみを頼りに正しい持ち方を身に着けることができます。
箸ホルダーを取り外せば、普通の箸として使うこともできます。シリコンホルダーもサイズさえ合えば、手持ちの箸に付け替えて使えるようです。
⑥箸匠せいわ 六角知能箸
鉛筆と同じ六角形の形により、安定して箸が持てると言われている六角知能箸。六角形という形に加えて、一般的な子ども用箸と比べて細め・軽めといった点も、持ちやすさのポイントとなっています。
素材は国産の自然竹を使用。ポリエステル塗装がされており、長期間使うことができます。
13㎝~17㎝まで用意されていますので、お子さんにちょうどよいサイズを選んであげられそうです。
⑦子ども用割り箸
滑りにくさ・つかみやすさという点では、割り箸もおすすめです。
箸先が四角い割り箸は、滑らずにつかみやすく、普通のお箸よりも「できた!」という経験を積みやすいと感じます。
子ども用の割り箸は、百円ショップでも手に入ります。市販のお箸で良さそうなのが見つからない…というときは、割り箸を取り入れてみてもいいかもしれません。
子どもにお箸の持ち方をどう教えるか
保育園や幼稚園では、「バンバンの手だよ」と言って教えてくれるところも多いですね。手で鉄砲を打つようなL字型にして、親指と人差し指のまたの部分に箸を1本置き、鉛筆を持つように指を添えます。

「お父さん指とお母さん指をくっつけるよ」といった声掛けをしてもいでしょう。最初は手を添えてあげると、子どもも理解しやすいです。嫌がるようなら無理せずに、様子を見ながら試してください。
いきなり2本のお箸を持つのは難しいため、最初は箸1本での練習がおすすめです。
上の箸を動かせればお箸の開閉ができるようになりますから、1本持ちに慣れておくと、2本にしたときに比較的上達が早いです。
1本持った状態で、手首や指を動かしてみます。指だけで箸を上下に動かせるようになれば、2本持っても上の箸だけを動かして開閉し、ご飯をつかめるようになります。

スプーンも使いながらじっくり時間をかけて、付き合ってあげてくださいね。
お箸と併用しよう!スプーン・フォーク選びのポイント

子どもが慣れないうちは、お箸だけで食事を続けるのは難しいですね。スプーンも使いながら進めましょう。この章では、スプーン・フォーク選びについて触れておきます。
子どもが持ちやすく食べやすい形状を選ぶ
理想的なスプーン・フォークは、以下のようなものです。
- 持ち手に滑り止めがしてある
- 子どもが持ちやすい太さである
- カーブが入っている
- 凹凸が入っている
- スプーンは適度な深さがある
- フォークは先端にギザギザや溝などの滑りにくい加工がある
「右手用」「左手用」と分かれているものもありますので、子どもの利き手に合わせて選びます。
利き手が分からないときは、ひとまず「右手用」を選び、成長に応じて合わないようであれば「左手用」を購入してあげると良いでしょう。
スプーン・フォークの素材について
スプーン・フォークの素材には、口にする部分が金属製のものが多いです。
保育園・幼稚園では、おかずを切り分けたりといった場面も出てきます。口に入れる部分が、プラスチックやシリコンタイプだと切り分けがしにくく、練習には不向きです。この場合は金属製がいいですね。
ただ、お子さんによっては、金属のヒンヤリした感触が嫌いな子もいます。嫌がる様子をみせたら、違う素材のものを試してみてください。
子ども用おすすめスプーン・フォーク2選

使いにくい食器は、子どもにも負担になります。できるだけ食事中のストレスを軽減してあげられるような、おすすめのスプーン・フォークをご紹介します。
①エジソンのフォーク・スプーン
エジソンのフォーク&スプーンのおすすめポイント
- 子どもの手に優しく、握りやすいデザイン
- フォークの先端部はギザギザになっていて、つるつるした食べ物でも落ちにくい工夫
- スプーンは面が平らで深みもある
- 汁物が飲みやすく、ごはんもきれいに食べきる
- 様々な種類があるので、子どもの好みのものを選べる
- 口に運びやすい角度
- 取っ手はラバー素材なので持ちやすい
②オクソートット(OXO tot)フォーク&スプーンセット
グリップ付きのフォーク&スプーンセットなので子どもの手にも持ちやすいです。
スプーンは汁物も食べやすいように深めの設計になっていて、フォークは先が丸く、子どもでも使いやすい設計になっています。
手先の不器用さに関係している感覚統合について

良いと言われるお箸を使ってみたけど、なかなかお上達しない。そんなときは小休止して、いつもと違う視点から子どもの様子を見てみましょう。
最後に、子どもの発達と関係がある、感覚統合についてご紹介します。「子どもの発達や不器用さが気になる」という親御さんでしたら、ぜひ知っておいていただきたい概念です。
感覚統合とは
人間の持つ感覚には、五感に下記2つを加えた7つの感覚が備わっています。
- 五感(視覚・聴覚・触覚・臭覚・味覚)
- 前庭覚
- 固有受容覚
前庭覚はいわゆるバランス感覚、固有受容覚は筋肉や間接の動きを感じる感覚です。
感覚統合とは、外部からの様々な刺激をこの7つの感覚で受け止め、脳で情報をまとめ・整理する働きを指します。この感覚統合のおかげで、私たちは日常生活で適切な動作や行動をとることができているのです。
発達段階にいる子どもたちは、感覚統合を繰り返しながら、体を動かしたり、道具をつかったりといったことを、ステップを踏んで習得し成長していきます。

この感覚統合がうまく働かないと、体のぎこちなさや手の不器用さといった形で現れることがあります。
ですので、発達に凸凹のある子どもが、お箸を上手に使えない等の不器用さに悩みがある場合、「感覚統合と関係しているかもしれない」ということを考えてみると、納得できる部分があるかもしれません。
感覚統合について少しでも知っていれば、子どもを正しく理解できるため、違った方向からのサポートもできるようになります。
感覚統合が上手く働くようにできること

感覚統合を上手く働かせるために、手先を含め体全体を使って思い切り遊ぶことは良い影響があると言われています。
屋外で遊べるなら、ブランコ、運てい、滑り台、縄跳び、ボール投げ、どれもすべて感覚統合を発達させるのにとても役立ちます。
屋内なら風船を蹴ってみたり、バランスボールやチャンバラごっこ等々、子どもが好きな遊びを取り入れてあげてください。
お手伝い好きなお子さんなら、一緒に料理をしたり、お掃除したりするのもいいですね。
お箸の練習が上手くいかないときは、お休みしながらでよい

子どもは本当に正直で、自分の興味がないことには見向きもしないことがよくあります。いろんな遊びを取り入れたり、前向きな関わりをしても、上手くいかないということもあるでしょう。
そんなときは「今は良いタイミングではないのかもしれない」と割り切って、お休みするのも一つです。
できないことに悩んでしまうと、気付かぬうちに無理強いしてしまうことがあるかもしれません。
上達がゆっくりでも、子どもがお箸を嫌がってしまわないように、楽しい遊びや食体験を繰り返しながら、「いずれ使うようになる」とのんびり構えることも大事です。
スプーンで食べられていれば、差し迫って困ることはありませんから、焦らずいきましょう。
まとめ
発達障害があるお子さんにも使いやすい、おすすめのお箸をご紹介しました。
- 箸やスプーンは、子どもが使いやすいサイズ・素材を選ぶ
- スプーンやフォークと併用しながら、その子のペースで進める
- 不器用さが目立つときは、感覚統合の視点から子どもの様子を観察してみる
道具選びがバッチリでも、なかなか思うように上達しないこともあるかもしれませんが、ぜひお子さんのペースを大事にしてあげてください。
楽しい食事時間を持ちながら、お箸が使えるようになりますように。