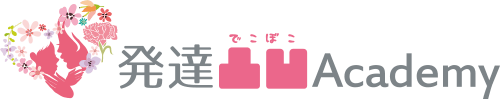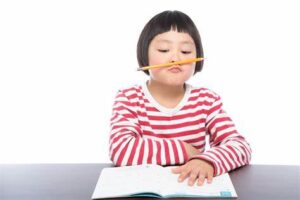雨の時、自然と傘を使うお子さんもいますが、傘をささないまま外に出ようとするお子さんも見られます。「傘をさして!」と声をかけても傘を使いたがらなかったり、最初は傘をさしていてもだんだんと嫌がったりする様子が出てくることはありませんか。
ここでは、傘を使いたがらないお子さんに隠された原因と親御さんができる対処法を考えていきます。
傘を使わない(使えない)のはなぜ?
傘を使ってくれないと雨に濡れて風邪をひいてしまうのではないか?と心配になったり、小学生になるまでには傘を使えるようになってほしいのに、どうして傘を使ってくれないのだろうか?と悩んでいたり苦戦している親御さんは多いと思います。
発達にでこぼこのあるお子さんは、発達の様々な特性から傘のような道具を使うことに苦手意識を持っている場合があります。
傘を使わない(使えない)理由と対処法について考えてみました。
傘を持つことが難しい
傘が上手に使えるようになるためには、傘を操れる握力や雨の方角に傘を向けて濡れないようにするバランス感覚などの運動能力が発達していることがポイントになります。
傘を持つ筋力が弱い・感覚が未発達
肩や肘、手首や手の筋肉の発達がゆっくりなお子さんの場合、傘を持って支えることが難しかったり途中で疲れてしまったりします。
また、傘をさすことができても、体幹が弱く姿勢が安定していないと、腕の筋肉が弱く真上に傘を持ち続けることができない場合もあります。そのため、傘を使っていても雨に濡れてしまいます。

同時に2つ以上のことをするのが難しい
「傘を持つ」「歩く」という2つの動きを同時に行なうことが難しい場合があります。加えて、周りにぶつからないように歩くという注意力も必要になってきます。
そうすると、傘をさそうと思うと歩けなくなったり、歩こうと思うと傘をさすことが難しくなったりしてしまいます。もしかしたら、傘の中から前が見えなくなって怖いという気持ちがあるのかもしれません。
興味が別の方向に向いてしまう
雨の日は水たまりや水しぶきなど、晴天時に比べて興味を引くものが多くなります。別の方向に興味が向いて、傘を持っているという意識が弱くなり、傘をしっかり持つ事が難しくなっていることもあります。

「雨が降る=傘をさす」が結びつかない
抽象的な表現が難しいお子さんにとって、傘をさした方がいい量の雨なのかを判断することが難しく、傘をさすタイミングに戸惑うことがあります。
また、雨に濡れる感触や雨を触りたいという欲求が勝っている事も考えられます。
傘を持つ感覚が苦手
指先や手の平に感覚過敏がある場合、傘の柄の感覚に苦手意識があり、傘を持つことを拒む場合があります。
傘の開け閉めや巻くのが難しい
傘を開く時に力が足りず開けなかったり、開くボタンを押す力が弱かったり、ボタンが押しにくかったりすることで、傘を使うことをあきらめてしまっている可能性もあります。
傘を開くことは難なくできるお子さんでも、傘を閉じる作業が難しい場合があります。片方の手で柄を支えて、もう片方の手で傘をスライドさせる作業や濡れた傘を巻いて止める作業は手先の器用さが求められてきます。また、手が濡れてしまうことに抵抗があるかもしれません。

親御さんにできる対処法
お子さんが傘を使わない理由として、
①「傘をさすことができない(難しい)」
②「傘をさすことはできるけれど、さしたくない」
どちらであっても親御さんにできる対処法をご紹介します。
傘を選ぶときに工夫をする
軽量の傘にしたり、風の影響が少ない小型の傘にしたりと、お子さんに合った傘を探してみるといいでしょう。
◎柄の種類
柄の感覚に苦手意識がある場合、ツルツルのプラスチックタイプやスポンジ製のやわらかいタイプ、木製タイプ、滑り止めをつけた傘など、お子さんに合った傘の柄を探してみるといいでしょう。


滑り止めのない傘の場合、滑り止めのキャップを挿入する方法もあります。
【楽天市場】カラーマーク【お試し】 傘 目印 滑り止め 盗難防止 名前 ネーム タグ レディース メンズ 子供用 おしゃれ かわいい アンブレラ マーカー 丈夫 安い ビニール傘 コンビニ傘 長傘 雨傘 日傘 折りたたみ傘 ジャンプ傘 ワンタッチ 持ち手 柄 グリップ カバー シリコン リング:カラーマーク楽天市場店 (rakuten.co.jp)
手が小さいお子さんには柄の部分が細いタイプ、力が弱いお子さんは柄が太い方が支えやすくて持ちやすく感じる事もあります。
◎開閉ボタンの有無
傘を開くときのボタンがお子さんにとって使いやすいものかどうか、弱い力でも楽に傘を閉じることができるかどうか、をチェックするのもいいですね。また、お子さんの危機認識や周囲への注意力があるかどうかによって、ワンタッチジャンプ傘か手で開く傘がいいかを判断材料の1つにするのもいいでしょう。

◎傘の種類
傘の中から前が見えるように、傘の一部がビニール製になっているものを選んでみるのもいいですね。

濡れた傘を触るのが嫌な場合は、逆さ傘を使ってみるのはどうでしょうか。
傘を巻いて止める時、マジックテープ式だとはがれやすくて巻き直しが続くようであれば、スナップボタン式の傘を選び、逆にスナップボタンだと留めるのに時間がかかるなら、マジックテープ式を試してみるのも1つの方法です。


折り畳み傘にする
長い傘の方がすぐに傘を開くことができるメリットはありますが、傘を巻いて止める作業が難しいお子さんの場合、折り畳み傘にしてみるのもお勧めです。折り畳み傘をたたまずに大きめのビニール袋に入れて、バックに入れてしまう方が楽な場合もあります。

傘を使うタイミングを決める
傘を使うタイミングがつかめないお子さんの場合は、『雨で顔が濡れてきたら傘をさす』、『少しであっても雨が降っていれば傘をさす』、周囲に意識が向けられるお子さんであれば、『周りが傘をさしていたら自分も傘をさす』など、ルールを親子で決めておくと、お子さんも迷わなくなるでしょう。

傘をさすときの工夫を伝える
お子さんはしっかり傘をさしているつもりでも身体が傘からはみ出ていることがあります。親御さんが見本を示してあげるとイメージがしやすくなるかもしれませんね。お子さんが傘をさしている時の様子を写真に撮ったり、濡れてしまっている部分を見てもらい、傘の位置の調整してみてはどうでしょうか。
傘をさすのが疲れるお子さんの場合、腕だけで傘を持つのではなく肩で支える方法、交互に傘を持ち替える方法など、親御さんが傘を使うときに工夫していることを伝えてみるといいですね。

お気に入りの傘を探す
雨などの刺激を楽しんでいるお子さんに傘を使ってほしい場合、お子さんが使いたくなるようなお気に入りの傘を一緒に探すのもいいかもしれませんね。
傘を使わない選択肢
傘が使えるようになる対処法をご紹介してきましたが、お子さんが傘を使うことを嫌がっているのであれば、無理強いをしないという選択肢もあります。
お子さんの特性によっては現段階の体の発達が未熟で傘を使いこなせない場合もありますし、お子さんは雨の刺激を楽しみたいと思っているかもしれません。また、『傘を使ってほしい』という気持ちや『子どもに傘を使わせない親』と周囲から見られることが嫌という親御さんの気持ちがあると思います。
しかし、その親御さんの気持ちと『傘をさしたくない』というお子さんの気持ちのどちらを尊重するかという視点に変えて、考えてみるのも1つの方法だと思います。
雨具は使ってほしいと思う時は、お子さんに「レインコート」と「傘とレインコートの併用」と「傘」どれがいい?
と選択肢を示して、自分で選んでもらうのはどうでしょうか。



まとめ
- 傘を使わないまたは使えない理由や背景をを知る。
- お子さんに合った傘を探したり、傘の使い方を伝える。
- 嫌がるなら傘を使わない選択肢もある。
傘を使わない背景には様々な理由があります。お子さんの体の発達を見ながら、傘が持てるように練習したり、傘を使って歩く練習をしたり、雨の日に少しずつ傘をさして歩く練習を重ねていくのも1つの方法です。
一方で、お子さんの「傘」に対する気持ちを確認しながら、傘にこだわらず、どの雨具を使うかを相談して決める方法もあります。
どの手段であれ、雨の日を楽しく乗り越えられることを願っています。